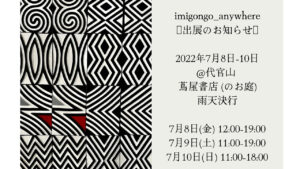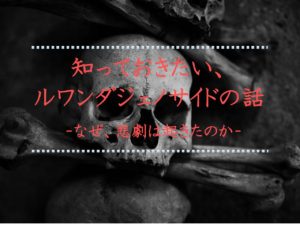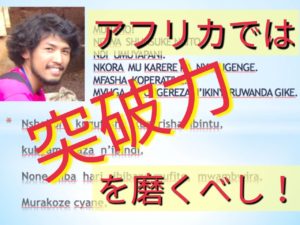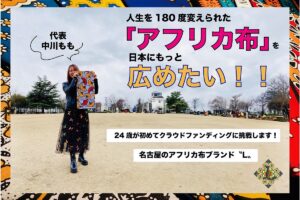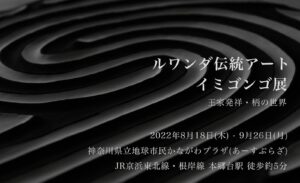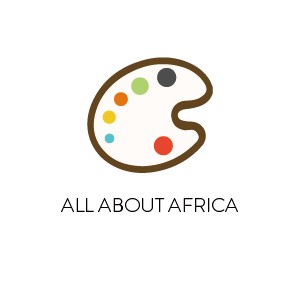「私たちのやってることには意味がある…!」とうれしくなるとき。
「今私たちがしていること、違うのでは?」とモヤモヤするとき。
NPOのスタッフが現地にいてどんなことを感じているのかを、素直にお伝えしていきます。
自己紹介

ウガンダで一緒に衛生環境改善を行う現地NGOのスタッフたちと
初めまして!NPO法人コンフロントワールドの副代表を務めている、溝口悠樹です。
弊団体代表の荒井の連載に続いて、私もALL ABOUT AFRICAにて連載を執筆します。
私が国際協力に関心を持ったのは約3年前、中東やアフリカからヨーロッパに避難する難民のニュースを耳にした大学4年の秋頃でした。
これを読んでくださっている方にも、地中海で船が沈み何千もの難民の方が亡くなったという話に衝撃を受けた方がいらっしゃるかと思います。
難民の方々をはじめ困っている人のために何かしたいという漠然とした思いから、大学で勉強していた物理から離れ、コンフロントに参画しました。
現在はタンザニアに住み中等学校の先生をしつつ、コンフロントの1スタッフとして、ウガンダの衛生環境改善に取り組んでいます。
ウガンダでの活動

貯水タンクを建設した小学校にて
私たちコンフロントはブタンバラ県という、首都カンパラから車で2時間ほど離れている地域で活動しています。
ここではトイレの普及率が25%のみとなっていて、トイレ外での排泄が人々の下痢症などを引き起こす原因の一つとなっています。
そのため私たちは現在、特に脆弱とされるHIV陽性の方々が暮らす世帯へトイレを建設しています。
また、昨年には水へのアクセスが悪い小学校に貯水タンクと浄水フィルターを作りました。
今年6月中旬、現在住んでいるタンザニアからウガンダに渡航し、その建設中のトイレを視察してきました。
私にとって人生初の、NPOのスタッフとして受益者の方たちとお話する機会。
そのときにあったこと、感じたことを素直に書きたいと思います。
現地で感じたモヤモヤ

お話した、二名の受益者の方たちと
建設中のトイレを視察しに、対象の世帯を訪問したときのこと。
トイレの仕組みや建設の方法について現地NGOから説明を受け、写真を撮り終えたあと、二名の受益者の方たちとお話する時間を作ることができました。私にとって初めての機会、分け隔てなく仲良く話したいなと、ワクワクしていました。
どのようにトイレ建設に参加したのか、トイレ建設以前にどのように用を足していたのかを彼らに聞いてみました。
しかし彼らはあまり返事をしてくれません。どうも緊張しているように見えたので、トイレとは関係のない話もしましたが、あまり反応してくれませんでした。
結局彼らとの会話は上手くいかず。
次の視察場所へ向かう直前、
とだけ、彼らから伝えられました。
今思えば、信頼関係もない中、いきなり外国人が来てトイレの写真を撮り始め話しかけてくる。
これにびっくりするのは当然のことです。私の話しかけ方も良くなかったのではと、思い返しています。
私にはおしゃべり好きなアフリカ人の友達がたくさんいるので、彼らとも仲良く話せるだろうと思っていたのです。そのせいか、去り際に伝えられた言葉に余計ショックを受けました。
「支援抜きの関係だったら、もっと対等に接することができていたかもしれない。トイレを作ることによって彼らは、これから与えられるのを待つだけになってしまうかもしれない。」
そんなモヤモヤが生まれました。
現地で感じた喜び

真ん中に立っているのが、私に「ありがとう」と伝えてくれたお母さんです
トイレを建設中の別の受益者を訪問したときのこと。3人の子どもとお母さんが暮らす世帯で、彼らは以前トイレを持っておらず、近所のトイレを借りて用を足していたそうです。
その受益者のお宅に着いてすぐ、お母さんが
と、笑顔で手を握りながら私に伝えてくれました。
人生で感謝を伝えられることは何回もありますが、このときの「ありがとう」は特別に心に残っています。
上に書いた2名の受益者の方とは打って変わって明るい雰囲気で出迎えてくれたこともありますが、そのときのお母さんのにこやかな笑顔が、忘れられません。
ある地域のHIV陽性者の方が暮らす世帯にトイレを建設するということは、はたから見ると小さなことかもしれません。それでもその小さなことは、そのお母さんにとってはすごく大きなことです。
だってこれからは、トイレを毎回近所に借りる必要がなくなるんですから!
モヤモヤを大事にする
このトイレ建設の費用はコンフロントが全額支払っています。
この場合、受益者がただ支援を受け取るだけになってしまう可能性があり、「自分の力で状況を良くするんだ」という気持ちが削がれてしまうかもしれません。
そのため今回は、現地NGOの方の監督のもと、世帯の住民の方々に建設に参加してもらうことで、「このトイレは私たちが作ったものだ」と彼らに認識してもらうよう工夫しています。
ただ、彼らにもっと主体性を持ってもらうことも可能かもしれません。
今回は現地NGO主導で住民が参加する形でトイレ建設を行ったのですが、例えばもし、トイレを作ろうと彼らだけで決め、主導できれば。
そして、低価格でできる建設の部分を彼らだけで行い、お金のかかる段階に差し掛かった時に私たちコンフロントが資金を出すという形にできれば。
いきなりトイレを作るために資金が下りてくる今よりも、受益者の自主性ひいては自尊心を大事にすることができるかもしれません。
上に書いた理想を実現するのは簡単ではないですし、もっと別のやり方があるかもしれません。
ただ、「これからのコンフロントの支援をどうしていきたいか」を考えるにあたって、このモヤモヤを大事にしたいと思うようになりました。
おわりに
私がNPOスタッフとして現地で感じることを、素直に書かせていただきました!
次回は、現地で頑張る現地の人たちのことを書きたいなと思います。
彼らの知識や地域との良い関係が支援活動には必須で、コンフロントがウガンダの衛生環境改善の活動をできているのは、現地の頑張る人たちのおかげなのです。
あくまでも主役は彼ら現地の人だという思いを、お話いたします。
ぜひ、次回も読んでみてください!
次の記事はこちら!☟